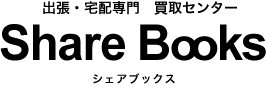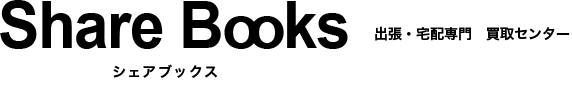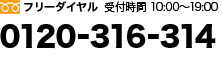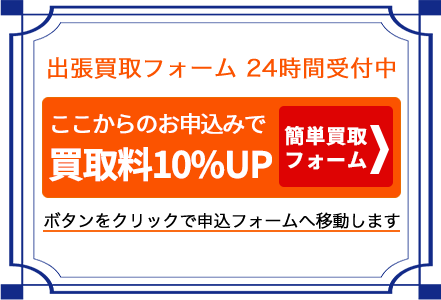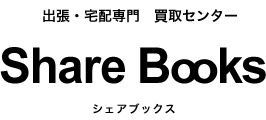普段読みたい本は、買取してきた本の中からやAmazonで探すが、久しぶりに本屋に行ったのでじっくり探す事にした。
2階建ての大きな書店だが、探し出してすぐに目に飛び込んできたのがこの本で、強烈なインパクトの表紙と題名に、他の本を探すことなく、その奇妙な表紙の本を手に取りものの数分で本屋を後にした。
本書はバッタ博士と言われ、バッタに食べられたいという子供の頃からの夢を叶える為に単身アフリカのモーリタニアに渡り、若き昆虫学者の奮闘を綴った渾身の一冊。
最初に言っておきたい。
この本が発行されたのは数年前だが、僕が今年読んだ本の中では一番面白かった。
虫が苦手な人は読まない方が賢明かもしれないが。。
子供の頃にファーブル昆虫記を読んで、偉大なるファーブルに憧れて昆虫の研究者になった著者。
冒頭ではポスドク(博士研究員)の身分で、昆虫学者になるべくアフリカへと旅立った
サバクトビバッタの研究をする為に向かったのは、西アフリカのモーリタニア。
サバクトビバッタはアフリカの半砂漠地帯に生息する害虫である。
バッタは漢字で「飛蝗」と書き、虫の皇帝と称される。
研究対象のサバクトビバッタはしばしば「神の罰」と称される大発生をおこし、農業に甚大な被害を与える。
ひとたび大発生すると数百億匹が群れを成して天地を覆いつくし、東京都程の広さの土地がすっぽりとバッタで覆いつくされる。
農作物のみならず、緑という緑を食い尽くし、成虫は風に乗ると1日100km以上移動するため、被害は一気に拡大する。
地球の陸地の20パーセントがこのバッタの被害に遭い、年間の総被害額は西アフリカだけでも400億円以上にも及ぶ。
バッタは特殊能力を持っており、環境次第で変身する能力を持っている。
まばらに生息している低密度下で発育した個体は「孤独相」と呼ばれ一般的な緑色をしたおとなしいバッタになる。
一方、高密度下で発育したものは、群れを成して活発に動き回り、黄色や黒の目立つバッタになる。
これらは「群生相」と呼ばれ、翅が長く飛翔に適した形態となり、黒い悪魔として恐れられている。
この現象をロシアの昆虫学者が発見し、「相変異」と名付けられた。
バッタ(Locust)とイナゴ(Grasshopper)は、この相変異を示すか示さないかで区別されており、相変異を示さないおとなしい日本のバッタは厳密に言うとイナゴの仲間らしい。
過去の歴史的なバッタの大発生は、決まって干ばつの後に大雨が降っている。
なぜ干ばつ後の大雨がバッタの大発生を引き起こすのかの著者の見解は以下の通りだ。
「干ばつによってバッタもろとも天敵も死滅し、砂漠は沈黙の大地と化す。生き残ったバッタはアフリカ全土に散らばり、わずかに緑が残っているエリアでほそぼそと生き延びる。
翌年、大雨が降ると緑が芽生えるが、そこにいち早く辿り着ける生物こそ、長距離移動できるサバクトビバッタだ。普段なら天敵に捕らえられ、数を減らすところ、天敵がいない『楽園』で育つため、多くの個体が生き延び、結果、短期間のうちに個体数が爆発的に増加していると考えられる」
なるほど。様々な条件が重なり、巨大な群れと成していくようだ。
ポスドク(博士研究員)は任期付きの身分の為、論文を発表して業績を上げなければ、研究者として就職する事が出来ない。
一介のポスドクが成果をあげないままアフリカで研究し続けることは難しく、あらゆる支援制度に頼らざるを得ない。
アフリカ現地での研究を続けたい一心で金策に走る中、京都大学の「白眉プロジェクト」を書いた章は秀逸だった。
京大総長の最終面接で、総長は「モーリタニアは何年目ですか?」という質問に著者は「3年目です」と答えた。
総長は「過酷な環境で生活し、研究するのは本当に困難な事。私は一人の人間としてあなたに感謝します」
この言葉で著者は泣きそうになったという。
まだ何も成果をあげていない一介のポスドクが単身アフリカで過酷な環境の中、つらい思いもしつつも奮闘している状況を全て見抜いての言葉だった。
京大の総長ともなると、やはり経験豊富で感性豊かで視野が広く、一言で人の心を掴む術を知っているなと感心させられた。
そして難関の白眉プロジェクトに見事合格し、収入面を気にする事なく研究できるようになった。
と、ざっと本の内容を書いたが、このような世界的に深刻なテーマがとてもポップに書かれてある。
センス抜群のユーモア溢れる文章と著者の狂気が見事にマッチされ、最初の数ページで見事に読み手の心を掴んでくる。久しぶりに冒頭から引き込まれた本だった。
研究対象のサバクトビバッタはその名の通り砂漠に生息しており、じっくり観察するにはサハラ砂漠で野宿をしなければならない。
砂漠を連想する一つにオアシスがあると思うが、オアシスといえば我々日本人のイメージでは、ヤシの木に囲まれた清涼感溢れる綺麗な水場で、とても快適な空間を想像してしまうが、実際のオアシスはドス黒く濁った水を茶色の泥が囲み、そのほとりには、水を飲みに来た動物たちの糞だらけで悪臭が漂っているらしい。イメージはただのイメージに過ぎない。
猛毒を持ったサソリに刺されたり、無収入の中バッタ研究がうまく進まなかったり、自身に降りかかる多少の不幸も全てコミカルに書いてあるが、その奥底にある凄まじい信念と探求心もしっかりと伝わってくる。
現地の研究所の職員との人間関係や自然に対する姿勢は尊敬に値するものであり、一つ一つの言動・行動・心理が本当に深くて感心させられる。
バッタ研究という、自身の心をこんなにも熱く燃やせるものに出会えている著者を羨ましく思う。
僕は文章で笑わせるというのは相当難しいと思っているが、この著者はいとも簡単に読み手を笑わせてくる。
こんな世界的に深刻なテーマだが、小難しい話は一切なく、コミカルに描写してくれている著者に聡明さを感じすにはいられない。
無収入に陥り、不遇の状況になりながらも自力で何とか対策を考え、全てはサバクトビバッタの為に行動に移していく。
当然だが、ほとんどの日本人はバッタ研究の重要性を認識していない。
そこで著者はまずバッタ研究の重要性を認知してもらう為に自らが有名になる事を考え、戦略的にあらゆるシーンで斬新な工夫くわえながら積極的に露出していっている。
僕がこの本をジャケ買いしたように、題名と表紙につられてこの本を購入した人は、まんまと著者の術中にはまったことになる。
連日、バッタを追跡する事で、無秩序に動いているように見えていた群れの活動にうっすらと法則性が見えてきて、バッタの次の行動が分かるようになってきたという。
現時点ではサバクトビバッタは殺虫剤での対策しかないらしいが、著者はそれ以外の方法での被害を食い止め方を見つけ出そうとしている。この本を読むと、この人なら出来るんじゃないかと思ってしまう。
個人的にはめちゃくちゃ面白かったので、今後も動向を追いかけようと思う。
2022年も有難うございました!
2023年もシェアブックスを宜しくお願い致します。